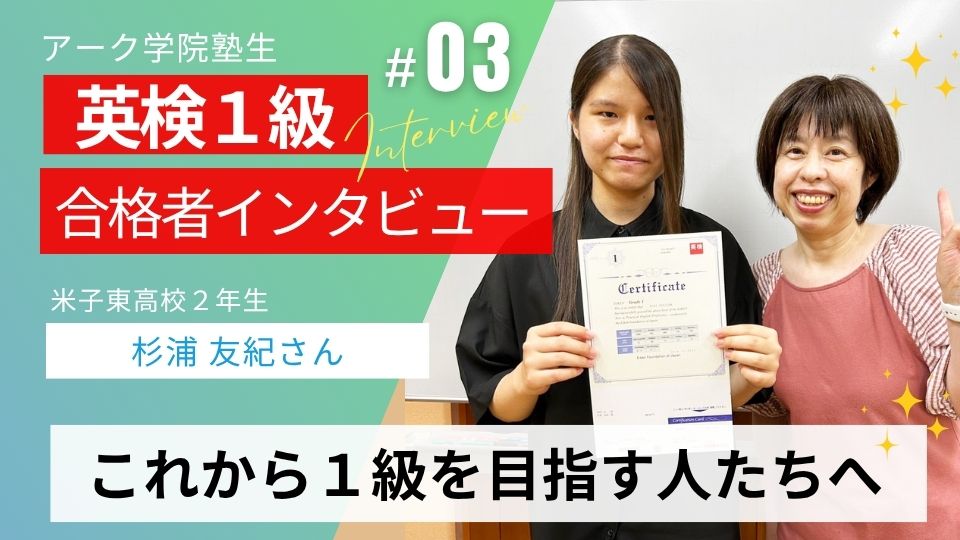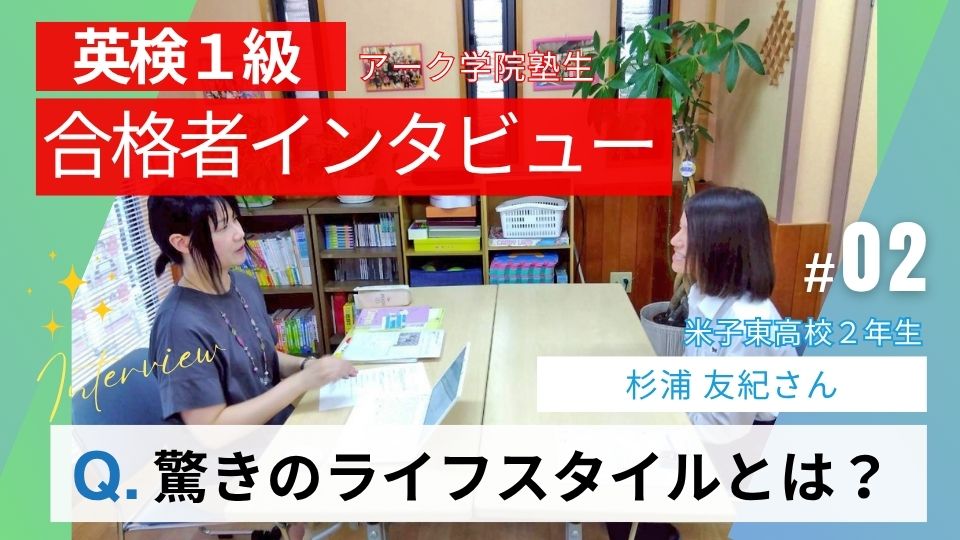インタビュー③:ライフスタイルと勉強習慣
ーーーライフスタイルへの取り組み、どんな風に勉強されたかを教えてください。
勉強時間の話ですと平日はおよそ4~5時間ぐらいしていました。週末になると、7時間超えてたような気がします。具体的には、朝4時に起きて大問3の長文読解を終わらせてから学校に行く準備をし、通学時間で単語を見て、授業間休憩で大問1の単語問題を解いて、昼休憩にリスニングを聞いて、放課後に作文を書いていたんですけど、合計すると4時間くらいですよね。家に帰ってから採点することで全部一日でできるようにしていました。
それに、英検は学校の定期テスト期間にかぶるんですね、毎回。英検も勉強しつつ、定期テストの勉強時間も取らなくてはいけませんでした。定期テストの直前では「筆記」を解く日、「リスニング」をする日と分けて少しだけ他教科の時間を作るようにしていました。放課後は合間を見て単語を勉強していました。
ーーー英検1級の単語となると、相当膨大な量ですよね。単語の勉強はかなり苦戦されたのではないでしょうか?
大変でしたね。今回英検1級への挑戦は実は3回目です。1回目と2回目と落ちてしまい、今回で丸1年でした。先程お伝えしたライフスタイルのこともあり「もうこれ以上続けると本当に疲れてしまう」と思ったので、今回がラストのつもりで頑張りました。

ーーー1年前から英検1級の勉強を続けられてきたということは、ちょうど高校1年生の時からスタートされたことになりますよね。高校入学されてから、中学校の時と勉強スタイルもガラッと変わるでしょうし、ますます大変でしたでしょうね。
これから一級目指される人には合格率6~10%っていう中で、かなり詰めて勉強しなければっていうようなところもありますよね。
はい、1回目と2回目のときより2~3倍ぐらい勉強量を増やしました。授業の合間や昼休憩に英検の勉強を取り入れて取り組むようにしてとにかく勉強時間を確保していました。
例えば、お昼休みが45分なんですけれど、英検1級のリスニングって35分間なんですよね。10分以内に食事を食べ終わって自習室に駆け込む…そういうライフスタイルを1年していました。
ーーーそれはすごい!でも、それくらいしなければっていう気持ちもあったんですね。
上野先生が、杉浦さんの勉強の様子について重ね重ね「言われたことを全部実行してアーク学院に来られていた」と言われていました。私はそれが大変印象的でした。ライフスタイルへの取り入れ方や、言われたことを全部しなければと考えられたきっかけみたいなのはありますか?
あの、自慢ではないのですが、英検準1級までは一発合格だったんです。各級大変なところはありましたが、こう「すごく頑張らないといけない」という瞬間は実はなかったんです。だからこそ1級は私にとって衝撃でした。英検1級受験の1回目、かなりの差をつけられて落ちてしまったんです。なかなか難しいんだなということを知った時に、勉強法を変えよう、やれることは全部やろうと思い切ることにしました。
でも、1級の勉強法や合格法となるとそもそも受験者数が少なく、情報そのものも少なくて困ってしまいました。そうしたら上野先生が英検1級に合格されて、勉強の仕方をすごく細かく丁寧に教えてくださったんです。一番信頼できる情報源だなと思ってたくさん取り入れさせていただきました。
●平日4~5時間、週末7時間以上の学習時間を確保
●朝4時起き・昼休み・通学時間など細かく時間を活用
●高校生活と両立しながら「今回が最後」の覚悟で挑戦
インタビュー④:苦労や工夫、得たもの
ーーー大変だったところ、勉強で工夫したところをもう少し教えてください。
大変だったところは、先程も言った通りで、急に難易度が上がったことです。「心が折れないように」を念頭に頑張りました。でも、本当に挫折しそうになったことが数え切れないぐらいありました。なので、なるべく近い目標を持って取り組むようにしましたね。
例えば、「今月いっぱいで6割取れるようになる」とかです。短期間に絞って、目標をクリアしていくのを意識していました。
そして工夫したところは「勉強法が合わない」と思ったら、すぐに変えるようにもしたことです。これまでの英検の勉強の感覚上で「なんか定着がいつもより遅いな」とか「なんか分かった気がしないな」っていうのが何となく分かってきていました。「なんかおかしいなあ」って思ったら、アーク学院の授業の日に上野先生に相談して、アドバイスをいただくようにしていました。
例えば、リスニングの勉強法なんですが、今までは「たくさん聴く」ということだけに集中していました。それに、今までリスニングは実は準1級まで苦労したことがなかったんです。でも英検1級のリスニングは聴いても聴いても入ってこないこととか、逆に細かくやりすぎて、時間を取りすぎることとかがよくあったんです。
どれが細かく勉強すべきところで、どれがやりすぎの練習法なのかを、第三者の意見として上野先生に選んでいただいていました。
ーーーここまで英検1級の難易度の高さに関する勉強法、取り組み方についてお聞きしましたが、面白かった事やためになったことも教えてください。
面白かったことは、正答率が上がってくると本当に何でも読めるようになってきたことです。例えば、海外や日本のニュースで、海外の中継が繋がってて、海外の大統領が喋っている場面が流れたとします。そういう発言なんかも全部聞き取れるようになって、なんか楽しいなって思うことが急に増えました。
ためになったことは、ちょっとかぶってるかもしれないですけど、学校の英語の勉強は全く困らないことです。共通テストで9割取るには英検準1級の力が要る、みたいな話を聞いたことがあるのですが、準1級が合格した頃は共通テストの制限時間に間に合わなくて、おかしいなって思う事もあったんですけど、勉強が分かり出してから10分余るぐらいで急に解けるようになりました。また、共通テストは読みながら聞くっていうのがあるのでそこは少し練習が必要だなと思いました。同じテストに対して印象が変わっていったっていうのがあったのが、自分なりに成長したという手応えに感じました。
●難易度の高さに何度も挫折しそうになるも、短期目標で乗り越えた
●勉強法を柔軟に見直し、先生の助言を活かして工夫した
●英語力が飛躍的に伸び、ニュースや学校英語への理解が深まった
インタビュー⑤:二次試験(英語面接)の勉強法と工夫について
ーーー1級の2次英語面接試験についてです。試験内容は自由英会話がまず最初にあって、その後指定されたものからトピックを選んでスピーチをし、その内容に関して面接官と英語でQ&Aをするという形式ですね。それぞれの工夫を教えていただけたらと思います。
自由英会話は、自分の得意分野をアピールできる場所だと考えています。できるだけ自分の得意分野の内容を伝えられるよう、「絶対にこれを話す」という内容を決めていました。対策ではその点を意識して、かなり力を入れて原稿を作りました。過去問の回答は一式作りましたね。
試験本番、最後のQ&Aで面接官の方からその練習していた部分に関する質問がありましたので、うまく相手に伝えられたのかなという手応えがありました。ある程度は、分かりやすい質問を投げかけてくださったんですけれど、実は何と言われたのか分からなかった質問も4つくらいありました。焦りましたが絶対に会話が止まらないようにして、できるだけ広範囲に対応できそうな回答をして対応するようにしていました。
ーーーそれは緊張されたでしょうね。緊張と言えば、英検1級の二次試験の試験会場は大阪だったとお聞きしましたが、鳥取から離れた試験会場での緊張というのはありましたか?
もちろん、知らない先生ばかりだったんですけど、想像してたよりもはるかにすごくフレンドリーな先生でした。自己紹介をしたらいきなり下の名前で呼ばれるぐらいで、すごくリラックスして話すことができました。
また、私がピアノのコンサートや発表会で定期的に演奏させていただいている関係で、本番や人に見られるという場面に強く出られたというのもあったと思います。それに大阪に行く用事も今までにあり、大阪そのものに慣れていたのもあります。場慣れしていた分、気負わずに出来たと思います。
●自由会話では「話す内容」を事前に決め、得意分野を伝える工夫を
●Q&Aでは質問が分からなくても会話を止めず、広く対応できる答えを意識
●ピアノの発表経験や大阪への慣れから、本番でも緊張せず臨めた
インタビュー⑥:アーク学院に通っていて良かったこと
ーーー杉浦さんは、小学1年生の時からアーク学院に通ってくださっています。アーク学院に通塾されていて良かったことを教えていただけたらと思います。
はい。先生方がすごく真摯で適切なアドバイスをくださったのがすごくありがたかったです。英検ジュニアや英検を順番に、小学4年生で5級を取得してから1年に1級ずつと目標に取得していったというお話をしましたが、そうなると学年相応の級よりも難しい級に挑戦することが多く、難しい教材からスタートすることになりがちです。英検をやってみて、教材の難易度も高くて、諦めてしまう…そういう現実は比較的ある話だなと思いますが、私の場合、もっと基礎的なところが分かっていないという感触を対策受講中に感じていました。
例えば、英検3級(中3レベル)では「過去形」や「現在完了」がどんどん登場しますが、まずこれが何なのかよく分かっていなかったですね。
アーク学院の先生に「もっと基本的なところが分からない」って伝えたときに、「そしたら別の問題集にしましょう」とか、「もう少し簡単なところから始めましょう」ってすぐに細かく対応してくださいました。それが良かったなと思いました。
ーーーありがとうございます。自分の学年よりも上の級に挑戦するときの、文法的な難しさは挑戦する生徒さんにとっては絶対に避けられないお話ですよね。当時は今よりずっと低学年向けの問題集も少なかったのもあると思います。その上、学齢的な難しさの他にも、「漢字にフリガナが書いてない」とか、そういった点の苦労もあるのではないでしょうか。
はい、英検2級(高3レベル)の勉強をしている時に、高校生と同じ授業で対策が始まりました。私は当時中学2年生で、高校で使っている文法書やワークを使ってみたら「漢字は読めない」「文法は知らない」「単語が読めない」だらけで…、本当に置いていかれてしまいました。当時、とても焦りましたね。アーク学院の先生に相談して、先程のような対応をしていただいて良かったなあと思いました。
●難しい級に挑戦する際、基礎が足りないと気づき柔軟に教材を変えてくれた
●学年より上のレベルに対応する際の不安や焦りを丁寧にサポート
●学習状況に応じた適切なアドバイスと調整が心強かった
合格者インタビュー③に続きます。